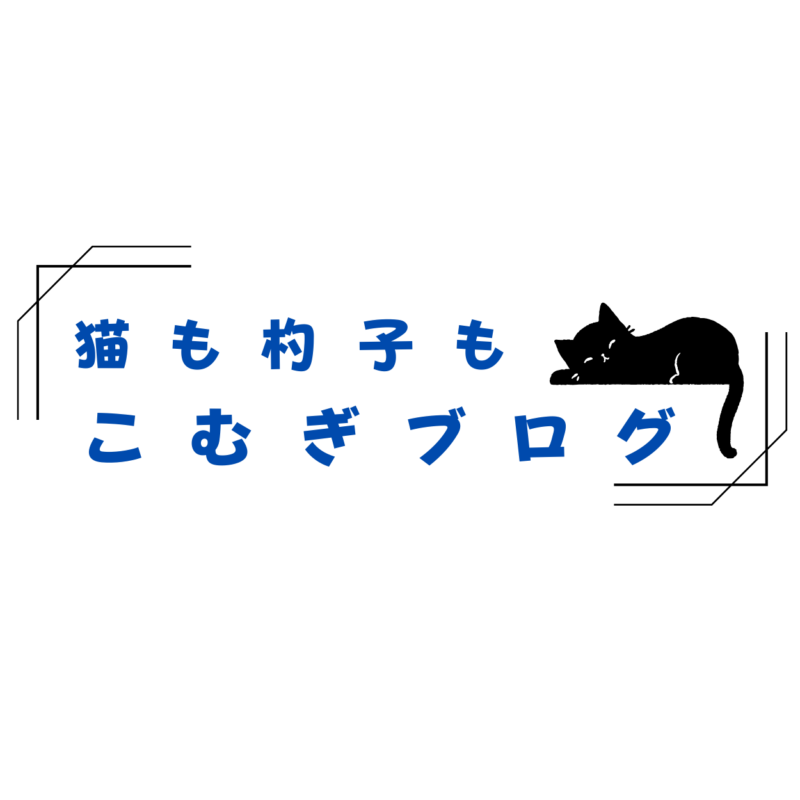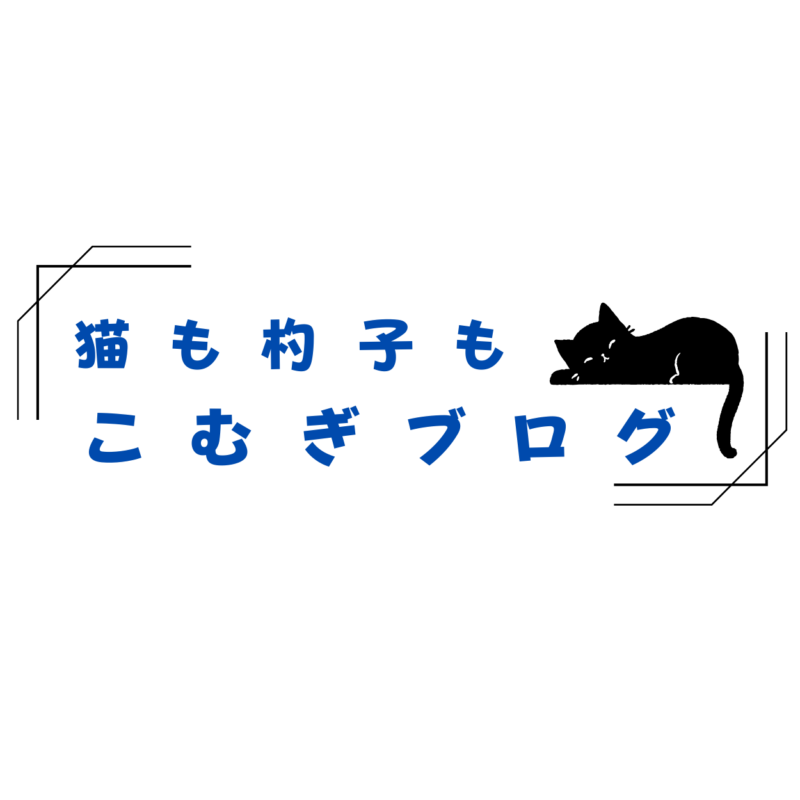夏場の雑草をリサイクル液で除草する方法



当ブログをご覧いただきありがとうございます。
この方法は除湿剤に溜まった水を利用します。ただし土壌にも影響が出ますので周囲の状況を判断して自己責任でお願いします。
上の写真は除湿剤に溜まった水を直接雑草にかけたものです、使い終わった除湿剤ですが捨てる前に少し手間はかかりますが家の廻りなどの雑草にかければ2日ほどで枯れてきます、その後草を抜いてゴミと一緒に処分します。
この作業をする際は必ずゴムの手袋をすることをお勧めします。
梅雨時や夏場に欠かせない「除湿剤」。押し入れやクローゼットに置いておくと、湿気を吸って容器の中に水がたまっていきます。
その水、いつも「捨てるだけ」と思っていませんか?
実はこの除湿剤に溜まった水を「雑草対策」に使うと、庭や駐車場に生える雑草の葉が枯れるという声があります。
一見「エコで節約にもなる便利な再利用方法」に思えますが、本当に安全なのか、植物や環境にどのような影響があるのかを知っておくことが大切です。
除湿剤の仕組みと溜まった水の正体
除湿剤の水ってただの水じゃないの?、ただの水ではありません。
除湿剤の多くは「塩化カルシウム」という成分で作られています。
この塩化カルシウムは、空気中の水分を吸収する性質を持ち、除湿が進むと容器の中に「塩化カルシウム水溶液」がたまります。
つまり、容器の中の水は「ただの水」ではなく、塩分(カルシウムイオンと塩化物イオン)が溶け込んだ液体です。
そのため、これを雑草にかけると、植物が浸透圧の影響で水分をうまく吸収できなくなり、枯れてしまうことがあります。
空気中の湿気(水分)を吸収することで、化学反応によりドロドロの塩化カルシウム水溶液になります。つまり、あの除湿剤の下に溜まっているのは:塩化カルシウム水溶液です。
水+高濃度の塩分(塩化カルシウム)
→ 実質「強い塩水」
除湿剤の水を雑草にかけるデメリット
土壌に悪影響を与える可能性
塩化カルシウム水溶液を土にまくと、土の塩分濃度が上がり、雑草だけでなく花や庭木など大切な植物まで枯れてしまう可能性があります。
環境へのリスク
雨で流れ出すと、周囲の土壌や排水に影響を与えることも考えられます。自然環境に配慮するなら安易に大量に使うのは避けるべきです。
容器の扱いに注意が必要
除湿剤の水は素手で触れると肌荒れの原因になることがあります。誤って子どもやペットが触れないように注意が必要です。
🌿 なぜそれを雑草にかけると枯れるの?
植物の細胞は、浸透圧のバランスで水分を保っています。
除湿剤の水は「高濃度の塩分水」で、これが植物にかかると:
- 植物の根から水分が逆流する(=脱水状態になる)
- 土壌のバランスが崩れ、根がダメージを受ける
- 根が水分や養分を吸収できなくなり、植物が枯れるという現象が起きます。
☠️ つまり、除湿剤の水は植物にとって「毒」
特に雑草は生命力が強いですが、それでも塩分濃度が高い水をかけられると、さすがに耐えきれずに枯れます。
ただし「除草剤」ではないため、全ての雑草に100%効くとは限りませんし、周囲の土壌もダメになる恐れがあるので注意が必要です。

パパ使い終わった除草剤溜まった水も除草剤になるんだね!

意外と効くから毎年夏の間は家の周りの雑草に使えるんだよ。
正しい使い方のポイント
- 狭い範囲でのピンポイント使用にとどめる
庭全体にまくのではなく、アスファルトの割れ目やコンクリートの隙間など、他の植物に影響しない箇所だけに使用しましょう。 - ペットや子どもが触れない場所で使う
使用後は水が残らないよう流すか、乾燥させる工夫をしましょう。 - 基本は「処分」が安心
再利用方法として紹介しましたが、あくまで一時的・小規模な使い道です。大量に処理したい場合は、自治体の指示に従って処分するのが最も安全です。
✅ まとめ
- 除湿剤に溜まった水の正体は、高濃度の塩化カルシウム水(=強い塩水)
- それを雑草にかけると、根から水分が奪われて枯れる
- 効果はあるが、土壌汚染や周辺植物への悪影響もあるので使い方には注意!
- また本体に切り込みを入れる際は液体が飛び散ったりするので注意してください。
- 家ではこの方法10年くらい前から、家の外壁の壁際など雑草がすごいので助かります。
- この廃液を巻く際は周辺の状況や特に近隣などに気をつけて撒くようにしてください。
除湿剤に溜まった水は「雑草を枯らす効果」があるため、ちょっとした再利用方法として注目されています。 - メリットとしては「雑草対策・節約・エコ」。一方で「土壌や環境への影響」「大切な植物まで枯れるリスク」「安全面の注意」がデメリットです。
- 家庭の庭や駐車場などで雑草が気になるとき、アスファルトの隙間など限定的な場所に試すのは有効ですが、環境や安全を考えると「大量利用は避ける」のが賢明です。
- 結論として、除湿剤の水は「使い道がゼロではないが、万能な雑草駆除方法ではない」ということを覚えておきましょう。