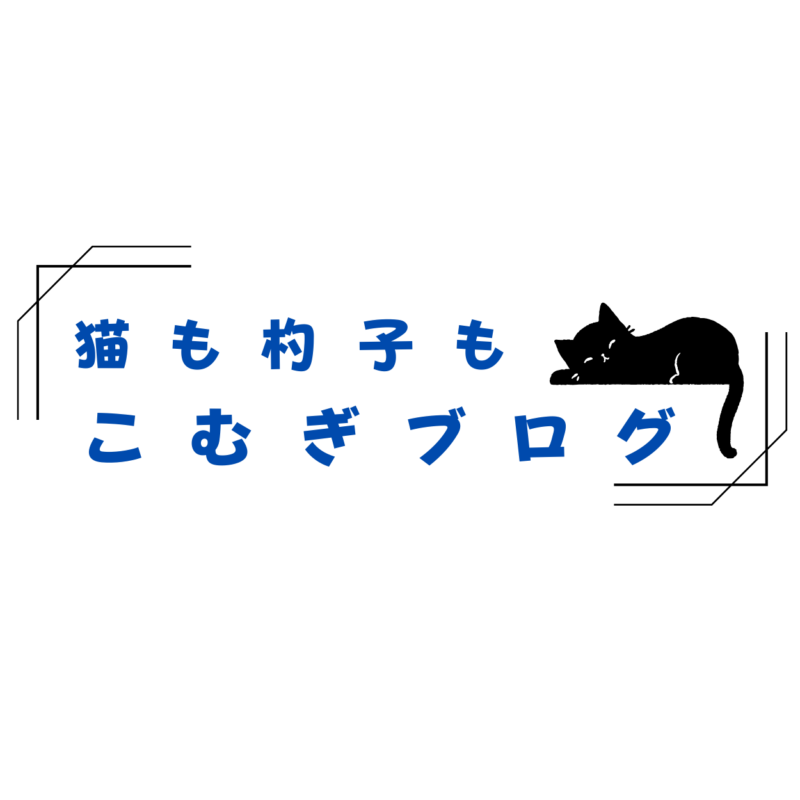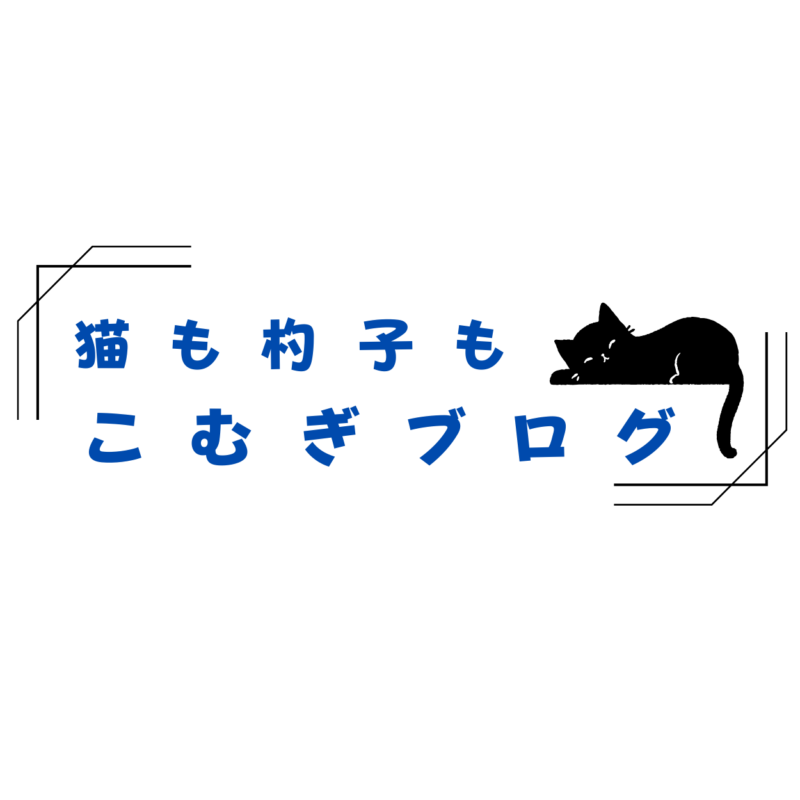“こむぎ”が教えてくれた、本能と感情のサイン
部屋の隅で「チッ」と言うこむぎ
「猫も杓子もこむぎブログ」を作る中で、毎日観察してると最近気づいたことがある。こむぎが部屋の片隅で一人時間を過ごしているとき、こちらが見つけると小さく「チッ」と舌打ちのような音を出すのだ。
これは威嚇なのか、本能的な反応なのか。それとも体調のサイン? 本記事では猫の音声・口周りの行動を科学的に分解し、舌打ちに“聞こえる”行動の正体を4つのパターンで整理。極学で調べた内容なので猫を飼ってる方の参考になればと思います。さらに家庭での観察ポイントと対処法を、ブリティッシュショートヘアという穏やかな気質が多いとされる猫種の個体差も踏まえて解説します。
「舌打ち」に見えやすい4つの行動

1) トリル/チルップ(短い「ルルッ」「ピッ」)=友好的・誘導
猫の「トリル」「チルップ」は、母猫が子猫を呼ぶときや、親しい相手への“挨拶”として使われる短い鳴き声。口をほぼ閉じたまま発する“murmur系”の声で、友好・興奮・注意喚起のサインとされる
こむぎが出す極小音がこれに近いなら、威嚇ではなく「見つけてくれたね」「ついてきて」の軽い合図かもしれない。じっさいこむぎの場合は威嚇と言うより見られたことへの怒り?何見てんの!!でも機嫌が悪いわけでもない。
2) チャタリング/チッタッ(小刻みな歯や顎の動き)=獲物興奮・フラストレーション
窓の外の鳥・虫・動く玩具を見たときに多い“カカカッ”という連続音。捕食本能に紐づく反応で、獲物への興奮や届かない苛立ちの表れとされる。しばしば鳥の声まね仮説も語られるが、学術的には仮説段階。隅で一人→飼い主を視認した瞬間に小さく鳴るのが習慣化しているなら、「見つかった!」という高揚や、次の行動(遊び・おやつ)への期待の表情かもしれない.
3) リップ・スマッキング(ペロッ/ぺちゃぺちゃ)=悪心・口内違和感の可能性
唇を鳴らす/舌を頻繁に出し入れする仕草は、悪心(吐き気)や口内の痛みでも見られる。食欲低下、過剰よだれ、嘔吐、隠れる行動が同時にあれば要注意。
加えて、**口腔疾患(歯根の痛み、歯肉炎、口内炎など)**は、食事・毛づくろい時の「カチッ」「ピッ」にもつながる。早期発見が鍵だ。
これもこむぎは当てはまらない
4) フレーメン反応(上唇がめくれる“くんくん顔”)=匂い解析
口を半開きにして上唇を上げ、ヤコブソン器官(鋤鼻器)に匂いを送る行動。新しい臭い・フェロモンに反応して一瞬だけ「変な顔」になる。威嚇ではなく情報処理だ。
これは何となく当てはまる。
威嚇(ディスタンス・インクリース)の合図は別もの
本当に距離を取りたい/怖いとき、猫は耳を伏せる・毛を逆立てる・低姿勢・尻尾を巻く・唸る/シャーなどの全身サインをセットで出す。これらは恐怖・不安・防御的攻撃態勢
「音」単体よりボディランゲージとの組み合わせで判断するのが科学的で安全。

こむぎケースの仮説:隅で“見つかる”→小さな「チッ」
ブリティッシュショートヘアは落ち着いた個体が多い一方、プライベート時間を大切にする猫でもある。隅で休んでいる時に発される「チッ」が微弱なトリルなら、
- 「今は一人時間だけど、確認したよ」
- 「(軽い)驚き→気持ちを整える自己鎮静」
- 「ついてきて/遊ぼう」の低強度合図
と解釈できる。逆に唇を鳴らす/頻回の舌なめずりが増え、食欲や元気が落ちるなら、悪心・口腔トラブルの線をチェックしたい。 - 今のところこむぎは食欲旺盛、元気なのでこれは一人の時間だと思ってます。
家庭でできる対処法(行動学×実践)
1) 近づき方の工夫
- 隅で休むこむぎには、目線を外し、横からゆっくり接近。直接正面は圧になる。
- 触れる前に名前→短いトリル風声かけ→指先で“においの挨拶”。成功体験を積む。
2) 予測可能性と選択肢を増やす
- **隠れ家(ボックス)・高所(キャットタワー)**を複数配置。
- 一人時間の**「安全地帯」**には、突然手を入れない。
3) 狩りごっこで出口を用意
- 釣り竿系おもちゃ→追跡→キャッチ→フード1粒で捕食シークエンス完結。チャタリングのフラストレーションを遊びで昇華。
4) 望ましい声にご褒美を
- こむぎがトリルで応じたら即座に褒める+軽い報酬。
- 「チッ」が強まり不快情動っぽい時は静かに距離を取る(望まない行動に報酬を与えない)。
5) ヘルスチェックのタイミング
- 口臭・よだれ・口元を触られるのを嫌がる・食べ方の変化があれば歯科検診へ。M
- 唇鳴らし+食欲不振や嘔吐が続くこの場合は病院を受診しましょう。
NG対応
- 音に驚いて叱る/追う/抱え上げる:不安を増幅し、真の威嚇に移行するリスク。
構いすぎ:回復の“安全距離”を奪うと、音が強化される。 - 「体調サイン」を放置:口腔疾患は進行しやすく、早期介入が予後を左右。
- 大きな声で怒鳴るなど!
まとめ|“チッ”は言葉。文脈で聴けば、もっと仲良くなれる
猫の「舌打ちに聞こえる音」は、友好のトリルから獲物興奮のチャタリング、さらには**体調サイン(悪心・口内痛)**まで意味が幅広い。
音+体のサイン+状況をひとつの文脈として読むことが、こむぎとの対話のコツだ。隅で過ごす一人時間を尊重しつつ、遊びで本能の出口を作り、違和感があれば早めに検診へ。
その積み重ねが、こむぎが安心して “声” を使える家をつくる。
こむぎが我が家に来てから約4ヶ月が経ちました。毎日、猫と暮らすことの新鮮さを感じており、犬とは異なる猫の習性や行動を理解した上で、こむぎにストレスを与えずに過ごせる環境作りを心がけています。私は猫初心者ですが、これからもこむぎと一緒に成長しながら、ブログで猫の情報を発信していきたいと思います。猫に関する本も調べてしっかり学びつつ、実際に経験したことを詳しく解説して、楽しく猫との生活を送るためのヒントをお伝えしていきます。